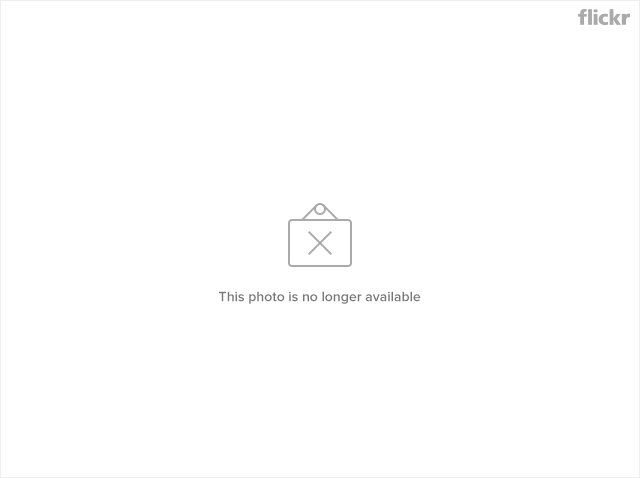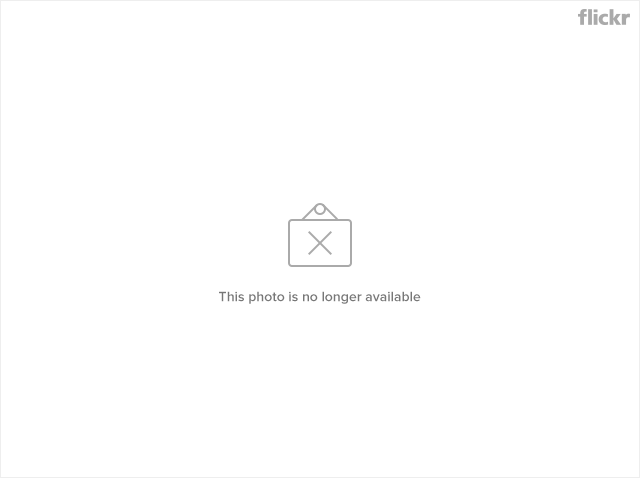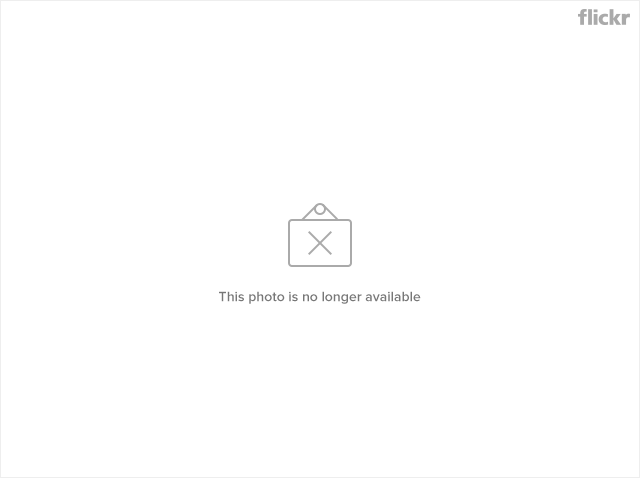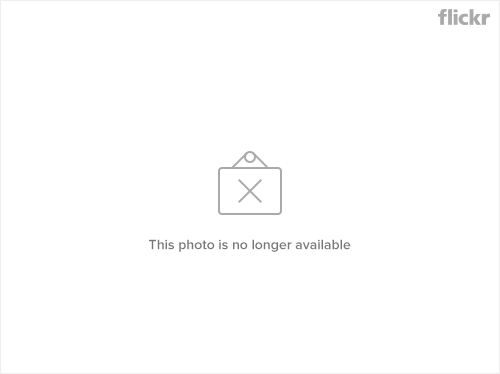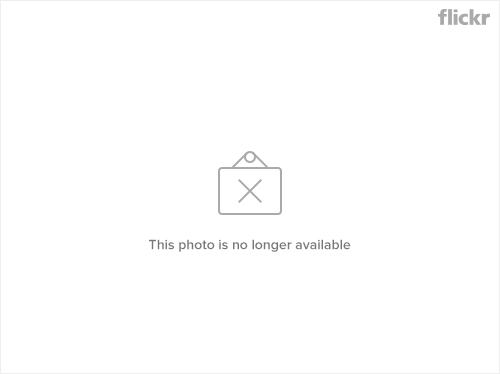タイトルのまんまなのだが、
最近長男が公文を頑張っている。簡単な問題をどんどん解いていくスタイルが結構楽しいようだ。
そこで弟にもやらせてあげようと、問題を自作。
ちゃんと花丸もつけてあげて、なんともほほえましい気分になった。
三重のおかげ横丁へ

おかげ横丁(おかげよこちょう)は三重県伊勢市の伊勢神宮皇大神宮(内宮)前にあるお蔭参り(お伊勢参り)で賑わった江戸時代末期から明治時代初期の門前町の町並みを再現した観光地である。運営は伊勢名物赤福餅を生産・販売する株式会社赤福の子会社である有限会社伊勢福が行う。 おはらい町の中ほどにあり、伊勢志摩を代表する観光地となっている。(おかげ横丁)

三重のおかげ横丁は一度足を運んでみたかった場所だ
この日は夏休み最後の終末、たくさんの人で賑わっていた
こんだけ集客できる魅力ってなんなのだろうか。
おはらい町の賑わいを通りながら伊勢神宮で参拝して、つまみ食いしながら帰路につくという特別な時間。
でもやっぱり観光地なだけあって、17時くらいにはほとんどのお店が閉まってしまったな。
ムスコたちは伊勢神宮で忍者ごっこしたときが一番盛り上がっていた。

夫婦岩(めおといわ、ふうふいわ、みょうといわ)・夫婦石(めおといし、ふうふいし、みょうといし)は、日本各地にある奇岩・名勝の名称。2つの岩が夫婦が寄り添うように見えることから名付けられる。海面から飛び出した岩と、山中の岩に大別できる。岩が3つ以上あって、そのうち2つだけを夫婦岩・夫婦石と呼ぶこともある。(夫婦岩)
ここは暗くなってから行ったが、行って良かったところ。見るだけで感動。
夫婦岩というのは全国各地にあるらしい。
とにかくカエルがたくさんたくさんいた
子猫とムスコたち
利根川を渡る橋のない県道・赤岩渡船に乗ってきた
赤岩渡船は千代田町赤岩から利根川をはさんで向こう岸の埼玉県熊谷市葛和田を動力船で結んでいる、主要地方道(県道)熊谷・館林線上にあります。利根川広しといえども現在3つしか残っていない利根川を渡る橋のない公道の1つです。そのうち主要地方道はこの赤岩渡船だけで、年間数千人の人々に利用されています。
赤岩渡船の歴史は古く、戦国時代、上杉謙信の文献にも登場します。その後江戸時代には水運が発達し、利根川を利用して江戸や房総方面との交通が盛んにおこなわれました。町内では赤岩のほか舞木、上五箇、上中森、下中森などの河岸と呼ばれる渡船場が栄えました。特に赤岩は水深もあり立地条件にも恵まれ、江戸からの大型船の終点という河川交通の要所として、坂東16渡津に数えられ繁栄に沸きました。
しかし、長かった繁栄も明治時代の中頃までで、その後は、鉄道等の交通機関が発達するにつれ急速に衰退し、渡船場として機能だけ残りました。各地の渡船場も廃止の一途をたどりましたが、この赤岩渡船は、ただ一つこの地域で残された数少ない河川交通手段として、人々に愛され、利用されて今に伝わっています。
大正15年県営、その後昭和24年から県委託事業として千代田町が管理運営を行っています。
(http://www.town.chiyoda.gunma.jp/kankou/akaiwa.htm)

橋のない県道、どうやって船に乗るんだろうか。

先程の乗船場でムスコと二人で待っていると・・・
「パパ、船が来たよ!」

自転車や原付も載せられるとのことだが、
その用途では想像より小型の船かも。
このへんからムスコちょっと不安になってきたようだ。
「・・・・」

船に乗り込んで、すぐに対岸まで出発。
ムスコはライフジェケット着用で去りゆく対岸を不安そうに見る。
「・・・(怖い)・・・」

船の通ったみち。言わば、これが県道なのだろう。

赤岩の渡し。

対岸をわざわざ船で渡ってきた目的はやはりジオキャッシング
宝物もムスコがすぐに発見!
誇らしげだなムスコ、少しだけ成長したかな。