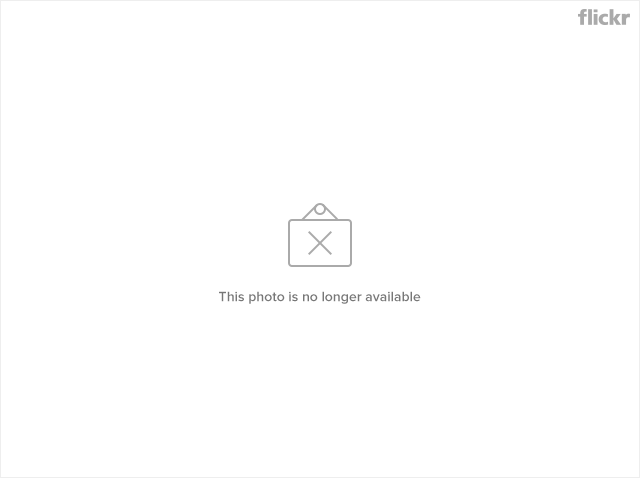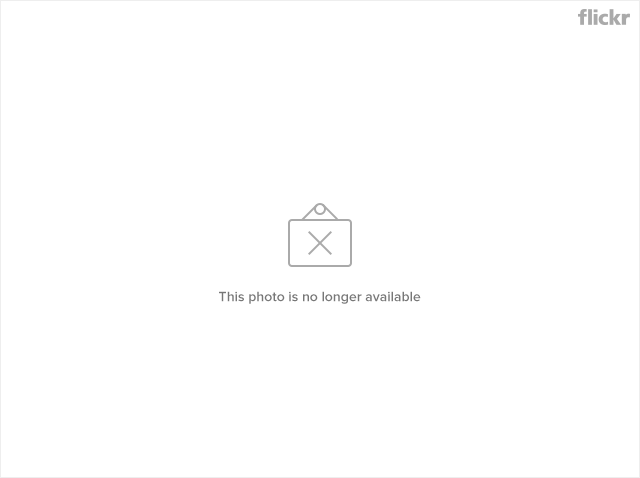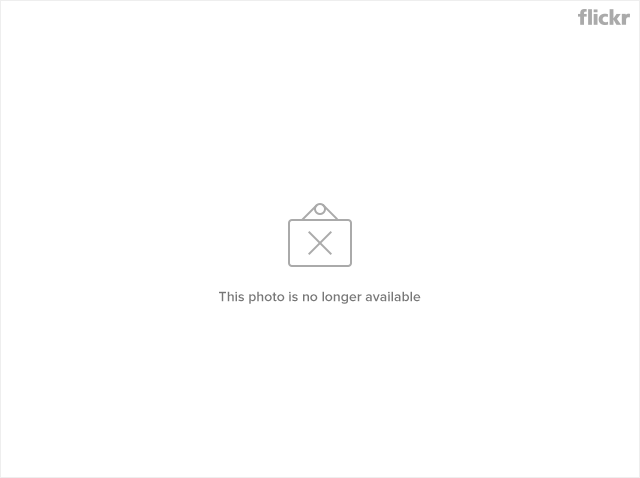ゴールデンウィークに家庭菜園をはじめる人も多いのではないだろうか。我が家も毎年親子でやっているが、ムスコたちも大喜びで参加してくれる。これは子育ての一環としてもとても有意義ではないかと思う。
長男「トマトときゅうりを育ててお弁当に入れるんだ。お友達のお弁当が足りなくなったらあげるんよ。」
次男「にんじん。にんじん。」
ちなみに、人参は育てていない。

特に5歳の長男は毎年やっているだけあって、すでに結構慣れている。
優しく苗をプランターに移す作業。これから自分で選んだ苗を自分のプランターに入れて育てていくのだ。

それは、2歳の次男も同じ。本当は人参を育てたかったらしいが、苗が売っていないし、たぶんプランターじゃムリっぽいので、小さなミニトマト。サントリーの本気野菜シリーズの「ベランダレッド」だ。本気野菜シリーズは素人向けなので育てやすく、すぐに売り切れてしまう人気商品のようだ。次男専用のプランターに自分で選んだ苗を自分で植えてもらった。美味しいトマトが出来るといいね。
さて、それ以外の今年のラインアップ。

まずは定番のトマト。これもサントリーの本気野菜シリーズで、「シュガーミニ」と「ピュアスイートミニイエロー」の2種類。黄色いトマトがどんな味なのか楽しみだ。ちなみに重曹を降りかけるとアルカリ性になって甘くなる?という本当か嘘かわからないツマの口コミ情報を参考にちょっとだけ重曹をかけてみた。これはワタシの担当。

次にナス。今年はナスにチャレンジしてみたかったので。だんたんナスのおいしさが分かる年齢になってきたっぽい。これも本気野菜シリーズにしようと思っていたけど、売り切れていたのでどこかのおじさんシリーズに。これもワタシの担当。

こちらのプランターではゴーヤ。窓の下に置いて緑のカーテンを作る予定。ゴーヤはあんまり好きではないのでちゃんと食べれるかは自信ないが、ゴーヤジュースにはチャレンジしたいと思っている。これも先程のおじさんシリーズに合わせてみた。これもワタシ担当。

こちらは、長男のミニトマト&きゅうり。長男セレクトの苗なので何を選んできたかはよく分からないが、きっと、愛着を持って育ててくれるだろう。

これが次男担当のさっきのミニトマト。

そして、最後にこれ。いちご。今の時期にいちご大丈夫?とは思うが、ちゃんと売っているし花を咲かせているのでまあ大丈夫だろう。長男がいちごを発見して喜んで選んできたので、もちろん長男担当。
今年もうまくいくといいなぁと思いながら、親子で家庭菜園を楽しみたいと思う。
今は海賊戦隊ゴーカイジャー、昔は太陽戦隊サンバルカン。

海賊戦隊ゴーカイジャーが近所のショッピングセンターに来ていたので、ムスコたちとしばし観覧。いわゆるヒーローショーだが、まだ始まったばかりで5人全員が揃っているのは珍しいかな。
長男「なんでテレビの中の人が広島にいるんだろう。広島には新幹線できたのかな。」
長男、いろんなことが分かっているんだか分かっていないんだか。ワタシが今の長男と同じ年の頃は「太陽戦隊サンバルカン」に夢中だったが、長男はそこまでではない。どちらかというと仮面ライダーの方がいいみたいだ。一昨年に電王が来たときの方が盛り上がっていたかも。
しかしサンバルカン、今見てもアクションの「キレ」が違う!ポーズをいっぱいマネしたな。黄色がカレー好きはこの辺から始まったんじゃなかろうか。

さすがゴールデンウィーク。近くでは大きな滑り台なども特設されていた。
1回500円と高額だが、かなり楽しんでいたのでよし。

ちょっと見えにくいけど、2歳の次男がピョンピョン跳ねて楽しんでいる。
こちらも大きなお兄ちゃんたちに混じって10分間ノンストップで飛び跳ねていた。すごい体力だ。
今年も家庭菜園の準備を開始。まずは土作りから。
いよいよ今日からゴールデンウィークが始まった。
今年は随分大型連休を取る人が多いが、ワタシは今年も論文作成。
毎年連休明けに〆切のある学会の研究発表会に投稿しているので、毎年連休中は論文を書いている気がする。
論文を書くために仕事をしているわけではないが、論文がかけるような視点を持って仕事を進めていきたいと考えている。

そんな中で今年も恒例の家庭菜園を始めようと思い、5歳の長男と一緒に土作りを開始。
昨年プランターで使った土をそのまま今年使うわけにはいかないらしいので、一度全部だして混ぜて天日干しを行う。混ぜる作業は長男の役割だ。砂場で培った技術がある。

ちゃんと耕うん車に乗ってしっかり混ぜる。

そしたら、なんか変な虫が出てきた。なんかの幼虫だろうか。
長男「気持ち悪い」
あれ、こどもって虫が好きなわけじゃないのか。でも確かに動きもちょっとアレ。

とりあえず、こんな時は図鑑で調べてみよう。
虫の図鑑はワタシが小さい頃に使っていたものを実家からもらってきたものだ。
ちなみに結局何の虫かはさっぱり分からなかった。
さて、次は培養土とか肥料を足してまたプランターに戻す作業となる。
実はまだ今年何を育てるかちゃんと決めていない。
土を干している数日の間に長男と一緒に苗を買ってこよう。
「育てる苗は自分で探して、自分で育てて、自分で料理して食べる。」
よし、今年のスタンスはこれでいこうね。
広島から岩手県釜石市に大ダンボール4箱分の衣類を届けました
私の妻が発起人となり、被災地である岩手県釜石市に住む友人を通じて女性物衣類を届けさせてもらった。妻の友人や近所の方、私の会社の女性メンバーからもたくさんの衣類をお預かりした。声をちょっとかければいろんな方がすぐに動いてくれるということをとても実感した。
震災から1ヶ月以上が経過しているが、被災地のニーズも「これから」に向けたものに変わってきているようだ。特に衣類関係などは市のHPを見ると避難所では足りているという情報もあるが、例えばとても若い女性が着れるようなものではなかったたり、毛玉がついているものだったりしているのが多いこと、なんとか仕事を続けている人は避難所に支援物資を取りに行くことができないしなどの現状があるそうだ。
特に今回の支援については、本当に必要なものなのか、かえって送ったことが迷惑にならないか、送った後の配布がかえって負担になってしまうのではないかなど、妻の友人と連絡を密にとりあって確認させてもらった。「これから」のニーズはこれからもどんどん変わっていくものと思うが、とりあえず「今」の思いが少しでも「これから」に役立ってくれたらいいなと思う。

—
ご協力頂いた皆様
この度は、急な呼びかけにもかかわらず多数の方にご協力頂きありがとうございました。
先日無事被災地へ届いたという連絡が入りましたのでご報告いたします。
私の友人の住む岩手県釜石市は今回の震災で特に甚大な被害を受けた地域の1つだそうです。
震災から1ヶ月が経過し、最低限の衣服などの支援物資は避難所に届くそうなのですが、
日常生活を過ごすための衣類(特に若い女性もの)が少なかったり、
なんとか仕事をはじめている人は避難所から支援物資を受取ることができなくなっているといった現状が、友人を通じて伝わってきました。
今回、皆さんから頂いた衣類はその私の友人を通じて、被災された方に直接届けてもらうことになっています。
皆さんの気持ちが被災地の皆さんに届き、これからの生活に少しでも役立ってもらるものと願っています。
■発送先:岩手県釜石市
■発送日:4/22(金)
■到着日:4/24(日)
■ご協力頂いた方:15名
■ご協力頂いた衣類:大ダンボール4箱分(女性衣類各種、ジャケット、子供服、マタニティー、男性衣類など)
※なお、梱包にあたっては種類別、サイズ別に再度仕分けさせてもらいました。
ご協力ありがとうございました。
発起人
幅員2mの双方向の自転車道~亀戸地区自転車通行空間モデル地区を見て

亀戸の自転車道は、今後の自転車道整備の様々な問題点を浮き彫りにした整備事例といえるだろう。ここは、国土交通省がこれから自転車通行空間をがんばってやっていきますという一番最初のモデル地区の1つ。つまり、全国の模範となるべく作られた自転車道なのだ。
だからこそ、「いいところ」と「問題点」の両面をしっかり見極めていくことが大切なんだと思うけど、休日の歩道橋の上からこの自転車道の整備を見たときの私の第一印象はすごい!よく出来ているじゃないかというもの。そもそも危険な自転車を歩行者との分離を図る目的で歩道から出すことが目的でスタートした自転車道整備というのは、歩行者の視点からみれば安全面では効果的かもしれないが、自転車ユーザーから見た大切な視点、つまり”走りやすさ”が根本的に欠けていると言わざるを得ないのかもしれない。この亀戸の自転車道はそういう意味でいわゆる自転車ユーザーからの批判がとっても多い。(ちなみに自転車道を頑張っていくという方針だけを聞いたとき、やっと自転車を歩道側にあげるための整備が進められるのかと思ったが逆だった記憶がある。)

道路をつくる側からの視点で言えば、すべての道路をつくる上での基準は「道路構造令」が絶対であり、自転車道の整備もこれに従わなければならない。亀戸の自転車道も道路構造令から見れば基準上の問題はないはずだ。道路構造令の自転車道の基準で最も分り易いのは幅員を2.0m以上とするということ。

バス停部付近の処理なんて、構造的にはすっごく考えられている感じがする。ここだけ見ると、視界も開けているし、歩道部との境界がもう少しフラットにしてすれ違いの問題さえ回避できたらいい感じになるかもしれない。

ただ、私の双方向の自転車道のイメージは、1人の幅しかない上りエスカレーターのすぐ横に境界のない同じ幅の下りエスカレーターがある感じ。普通に止まってのっている時には全然問題ないけど、いつはみ出してくるか分からない中でちょっと急いでいたり、誰か一人でも抜かしながら来る人がいるとすっごく危ないみたいな感じだろうか。

交差点では自転車通行帯を必ず通行できるように広めの滞留空間が整備されている。自転車が車の信号に従うべきなのか歩行者用の信号に従うべきなのか曖昧な現在(自転車通行帯が横断歩道の横に併設されていたら歩行者信号でそれ以外は車道の信号に従うのが原則のはず)では、交差点部の自転車の安全対策を考えるならこれは有効な処理といえる。

雨の日の翌日、この水たまりを通らなくちゃいけないというのは酷なことだろう。どうもこの区間は排水が悪いようだ。
通行している様子を見てみるといろんな問題も見えてくる。
【いいところ】
・路上駐車で使われていなかった車線を自転車専用道として整備したこと。今までこんなにしっかり整備したところはなかった。
・交差点部やバス停部など、これまで結構曖昧に整備していたところを連続的な自転車通行空間として上下線ともに確保したこと。
・国道14号という大型車の多い路線にガードパイプと縁石ではっきり車道と分離した空間を確保したこと。
・自転車道の整備により歩道は歩行者のためのものであって、自転車は通行してはいけないことを大きな声で言えるようになった。
・車道を通行する自転車が守るべき信号はクルマと一緒だけど、自転車通行帯があるところは歩行者と同じ信号を守ってもらうことを物理的に誘導させたこと。
【問題点】
・自転車道にしちゃったら、自転車はここしか通ってはダメということ。歩道も車道も通ったらダメ。強制的にここを通りなさいと言われている。だから、スピードの合わない自転車を抜かすことなんてダメだし、エスカレーターに乗っている時のようにずっと前の人の後ろについていくしか許されない。つまりその方が安全でしょうという原理を押し付けられている。
・縁石とガードパイプで挟まれた2mの空間での双方向通行はまったく逃げ場がない。途中から自転車道に入ることも出ることもできない。平日の通勤通学時の現状を考えるとかえって危険も。
・荷さばき車両がうまく止められなくなってしまって、結局さらに1車線まではみ出して停車しているという危険を招いてしまっている。
【今後の課題】
・自転車道ではなくて自転車レーン+自転車通行可歩道の方がいい?
・というか、自転車道の遵守率が上がらないと作っても効果が発現しない
・2mの双方向はやっぱり狭い。使いにくいから走らない?裏道を通る人も増えてしまう。
・自転車道にするなら、歩道との境界はもっと緩やかに
・荷さばき車両の停車帯への対応を考えておかないと
・結局は部分的な通行空間整備に意味がなく、乗りやすい自転車走行空間が必要
【まとめ】
安全性を重視するところはもちろん重要だけど、自転車の走行性を考えること。例えば交差点部の安全面だけをみたら、亀戸の事例は素晴らしいけど、じゃあ毎日ここを通って通勤したいかって言えばいやじゃ となる。周辺ネットワークと整備レベルをどうすりあわせていくかということが一番重要になってくるようだ。トレードオフ問題なので、答えは1つにならないところが難しい。だからこそ、自転車ユーザーの一人として熱く、コンサルとしては冷静に考えていきたいところだ。